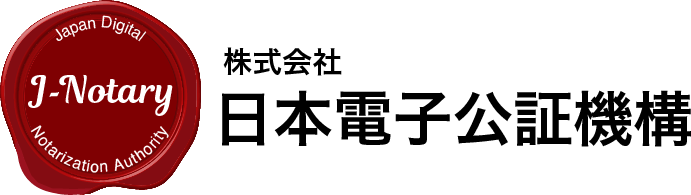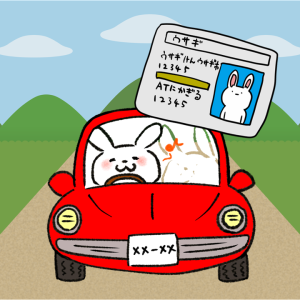企業の秘密管理に潜むリスク:裁判例から学ぶ営業秘密の守り方
企業の重要な知財の中でも、自社独自の技術など秘密に保管しているのが<営業秘密>です。
その<営業秘密>が盗まれて、他社に横流しをした元社員を訴えたところ、”無罪判決” となったケースがあります。
盗まれたのにも関わらず、なぜ無罪になってしまったのでしょうか?
その理由と企業がするべき対策についてお伝えします。
<営業秘密>とは
<営業秘密>とは、企業が自社の事業や商品開発において秘密にしている重要な情報のことです。
例えば、新しい技術や製品の設計図、顧客リスト、価格情報などが含まれます。
これらの情報は、適切に管理し漏らさないことで、競合他社との差別化やビジネスの優位性を保つために非常に重要です。
法律で保護されており、不正に持ち出されたり漏洩した場合は法的な責任を問われることもあります。企業にとっては、<営業秘密>を守ることが、長期的な成長と競争力の維持に欠かせない重要なポイントです。
不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。
そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の<営業秘密>として管理されていることが必要です。
<営業秘密>の要件
不正競争防止法では<営業秘密>について、
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不当競争防止法2条6項)
と定義されています。
つまり、企業が持っている情報が<営業秘密>に該当するためには、
① 当該情報が秘密として管理されていて(秘密管理性)
② 事業活動に有用なものであり(有用性)
③ 公然と知られていないこと(非公知性)
という3つの要件が必要になります。
これを<営業秘密>の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)といいます。
こんなことをしても無罪になってしまう
ここからは、企業の情報を持ち出したり、企業の情報が盗まれてしまったのにも関わらず、裁判で “無罪” になった判例をご紹介します。
【訴訟①】
- A社の販売価格の情報を社員Xが知人Yに漏らした。
- 販売価格の情報は社内のシステムから入手した。
- システムを利用するには、ID/パスワードでログインする必要がある。
この案件では、<営業秘密>にあたる情報以外の日報や在庫数など通常業務で利用するデータも同じ社内システムで一緒に管理されていたため、従業員に対し、販売価格の情報が企業の秘密情報であるというアピールが十分に行われていなかったとして “無罪” となりました。
【訴訟②】
- S社が販売している機器のプログラムにN社のアルゴリズムが使用されているということで訴えた。
- 対象のアルゴリズムは営業担当が顧客説明用に作成したハンドブックに記載されていた。
- ハンドブックには「Confidential」や「社外秘」といった記載がされていた。
この案件では、対象のアルゴリズムが<営業秘密>にあたるかどうかがポイントになりました。
アルゴリズムが記載されているハンドブックは顧客に説明する際に利用されており、ハンドブックに秘密ではない公知の情報も一緒に記載されていたことから、こちらも「秘密管理性」が十分ではないということで “無罪” となりました。
【訴訟③】
- T社で働いていた社員が営業秘密の含まれた教本を複製して持ち出したということでT社が起訴した。
- 教本は、閲覧コーナーに、他の本と共に、表紙の全部又は一部が見えるように展示されていた。
- 閲覧コーナーには監視員はおらず、周囲に監視をすることが可能な職員もいなかった。
- 教本を紐や鎖でオープンラックとつなげるような措置もなく、閲覧するために氏名等を記載するなどの手続もなく、館内に入った人は誰でも自由に手に取って閲覧することができ、メモをすることも禁止されていなかった。
- 教本は若手従業員の育成講座のテキストとして使用され、受講者には終了後に教本が配布され、持ち帰りも許されていた。
前の2つの訴訟と同様、社員に対して対象の情報が秘密であることをアピールできてないということで “無罪” となりました。
企業としてとっておくべき対策とは
“無罪” となった訴訟を紹介しましたが、いずれも「秘密管理性」の不足が原因となっていますので、企業としては社員に対して、秘密の情報であるということをしっかりと理解してもらう仕組みが必要になります。
1. 明確なルールとポリシーの策定
- 営業秘密の定義と範囲を明文化し、全社員に周知徹底。
- 保護対象の情報を分類し、取り扱い基準を設定。
2. 契約の締結
- 従業員や取引先と秘密保持契約(NDA)を締結。
- 契約内容に情報漏洩防止や違反時の罰則を明記。
3. 情報アクセスの制限
- 必要最小限の従業員にのみアクセス権を付与。
- パスワード管理や多要素認証を徹底。
4. 物理的・技術的セキュリティ対策
- サーバーやデータの暗号化。
- 物理的な施錠や監視カメラ設置。
- USBや外部記録媒体の使用制限。
5. 従業員教育と意識向上
- 定期的な秘密保持研修を実施。
- 情報管理の重要性を徹底させる。
6. 監査と管理体制の強化
- 定期的な情報管理状況の監査。
- 不正アクセスや情報漏洩の兆候の早期発見。
7. 情報の持ち出し・退職時の管理
- 持ち出し記録の管理と監査。
- 退職時の情報持ち出し禁止や回収。
8. インシデント対応策の整備
- 情報漏洩時の対応マニュアル策定。
- 迅速な被害拡大防止策と報告体制の整備。
弊社では、営業秘密を含む企業の重要情報管理を目的としたソリューションを提供していますので、ぜひ一度、ご相談ください。